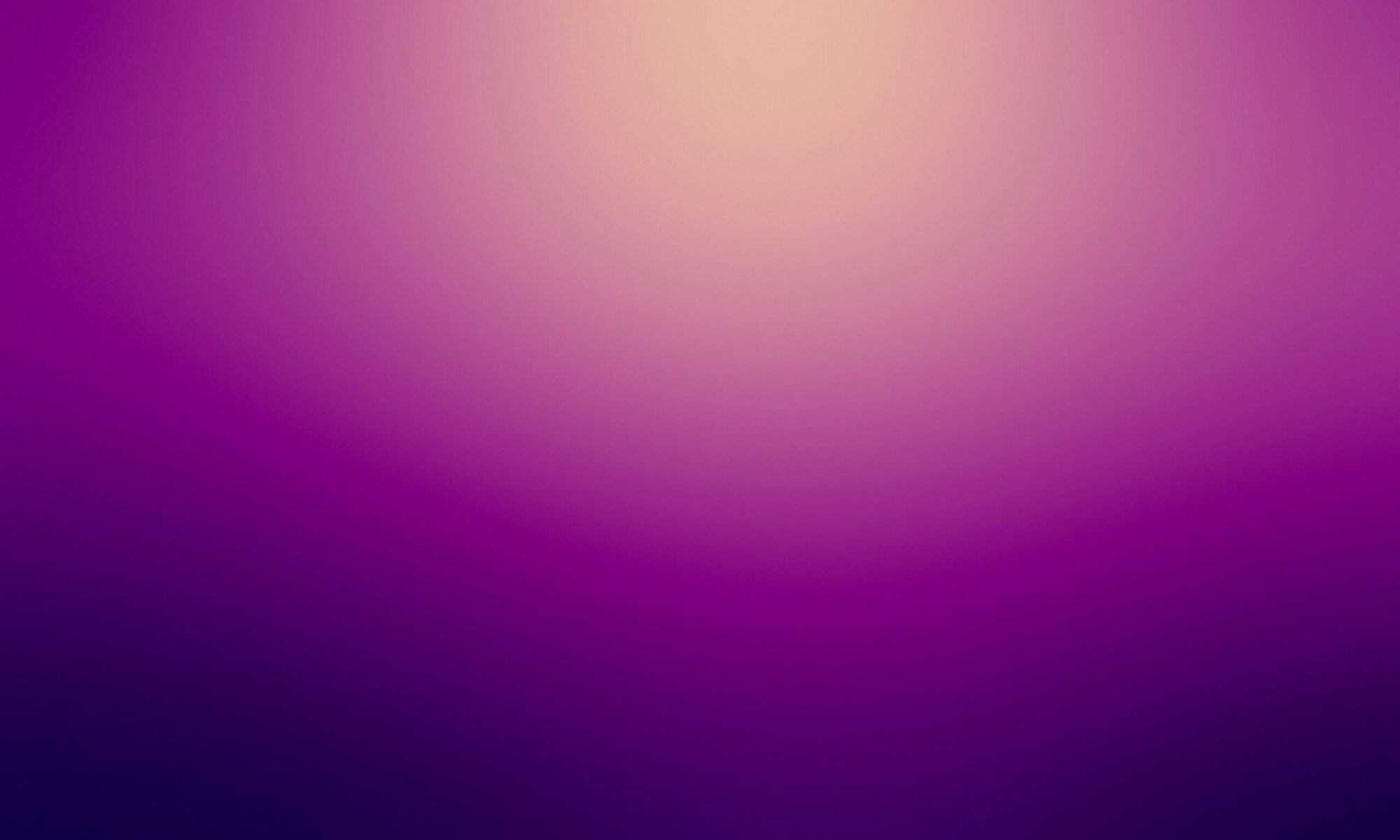「棚」の次は「人」──伝わらない商品の魅力
販売員はすべてを知っているわけではない ドラッグストアで商品を選ぶ際、消費者は販売員にちょっとした説明やおすすめを求めることがあります。しかし、販売員がすべての商品について深く理解しているとは限りません。
ときには、**不完全な知識や個人的な好み(バイアス)**によって特定の商品だけが推されてしまうことも…😅
メーカーがこだわって作った成分の違いや機能性のポイントが、現場では十分に伝わらず、消費者の記憶にも残らないまま終わってしまうことがあります。
“売りやすさ”が優先される現場 販売員が重視するのは、あくまで「今日、売りやすい商品」。それは、価格が安い・よく売れている・キャンペーン中といった条件を持つ商品です。
たとえメーカーが「この新製品は優れた技術で…!」と力を入れても、 店頭ではその魅力が置き去りにされることも少なくありません💦「伝えたい」と「伝わる」の間には、大きなギャップがあるのです。
“現場の声”が届かないジレンマ さらに問題なのは、販売員の声がメーカー側に届きにくいこと。 例えば――
-
「この商品、手に取る人多いけど説明が難しい」
-
「香りが強いって言われることが多い」
-
「リピーターが増えてきてる」
こうした現場のリアルな声が、仕組みとしてメーカーにフィードバックされることはほとんどありません。その結果、現場での小さな気づきやヒントが商品改良に活かされないという、もったいない状況が続いているのです🤔
伝えるべき相手は“棚”だけじゃない 店頭での成功は、「目立つ棚位置を取ること」だけではありません。 “販売員というメディア”をどう活かすかもまた、重要な戦略の一つです。
メーカーと販売現場が、もっと相互に情報をやり取りできる仕組みがあれば―― 伝えたい商品の魅力が、実際に“選ばれる理由”として伝わる日も近づくはずです✨
次回は、こうした課題に対して、どんな工夫やアプローチが考えられるのか?実際の取り組み事例も交えて掘り下げていきます(続)