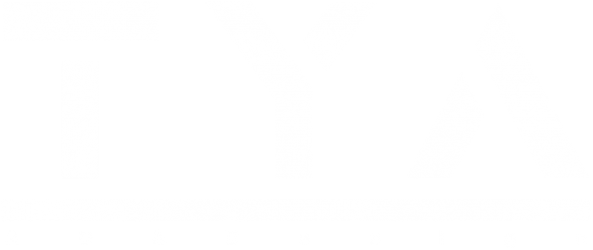香港の街を歩いていると、目を奪われる風景があります。それは、超高層ビルの外壁を覆うように組まれた、網目状の竹足場。細い竹が、まるで建物に寄り添うように、空へ向かって軽やかに伸びていく。この光景を初めて目にした訪問者は、思わず足を止めて見上げることでしょう。
実は、香港ではいまも約80%の建設現場で竹足場が使われていると言われています。この技術は、100年以上にわたって受け継がれてきた伝統であり、 単なる工法を超えて、都市の風景の一部、ある種のアートとすら感じられます。
🏗 なぜ、いまも竹なのか?
香港のような密集型都市において、竹足場が選ばれ続けている理由は、単に「伝統だから」ではありません。
-
軽量で柔軟性があるため、設置・撤去が迅速に行える
-
複雑な建物形状にも対応しやすく、狭い場所でも施工が可能
-
コストが比較的抑えられる(特に資材面)
-
湿度の高い気候でも、竹は滑りにくく、作業性に優れる
こうした実用的な利点が、竹足場を今日まで現役の技術として存続させている理由です。単なるノスタルジーではなく、現場の合理性に根ざした選択なのです。
👥 技術継承の危機と労働力の高齢化
しかし、この伝統技術もまた、時代の変化に直面しています。現在、竹足場業界には約4,000人が従事しているとされますが、その多くが高齢であり、若い世代の担い手が少ないことが深刻な課題となっています。
建設現場での安全性や働き方そのものが見直されるなか、「危険」「きつい」「未来が見えない」といったイメージが若者の参入を阻んでいる現実もあります。
また、仮に金属足場への切り替えを検討した場合、材料費や施工工程の増加により、コストが大幅に上がる可能性が指摘されています。とはいえ、明確な比較データが不足しており、移行の判断材料が揃っていないのも現状です。
🛠 事故の本質は“素材”ではない
竹足場に対しては時折、安全性を不安視する声もあります。しかし、竹足場労働組合はこう主張します。**「事故の多くは、素材そのものではなく、現場での管理体制や配置の不備に起因する」**と。つまり、安全の鍵は“竹か金属か”という選択よりも、安全基準の徹底と、作業員への教育・訓練の充実にあるというのです。
この指摘は、伝統技術を守りながら、現代の安全基準にも対応していく上での重要な視点です。素材だけを変えるのではなく、運用の質そのものを高める視点が求められているのです。
🌆 都市の一部としての“竹足場美学”
香港の街には、狭い路地の上、歴史ある建物の外壁、あるいは建設中の高層ビルに至るまで、さまざまな場所に竹足場が組まれています。
その姿は、単なる工事用の設備ではなく、「都市と人間の関係性」を象徴する存在にすら見えてきます。
細く、しなやかで、自然由来の素材でありながら、都市のスピードと高さに見事に適応している。その佇まいには、香港という都市が持つ柔軟さと強さが表れているように感じられます。
🗣 あなたはどう感じましたか?
竹足場は、いまも香港の風景に息づく“生きた伝統”です。けれど、その継承には時間がかかり、人の手と意志が必要です。
あなたが香港を訪れたとき、ビルの外壁に編み込まれた竹の網目に、どんな思いを抱くでしょうか?
未来にこの光景を残していくには、私たちの「気づき」と「選択」も問われているのかもしれません。 ■香港でのマーケティングインサイト調査もTYAにお任せください