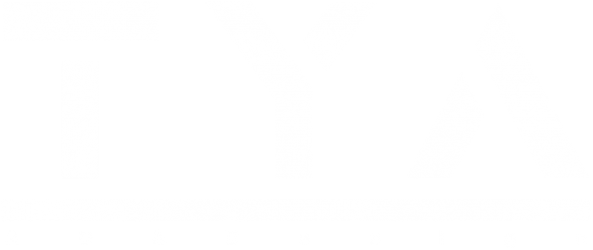(承前)
香港は昔から外食文化が盛んな土地です。共働き世帯が多く、キッチンが小さな住宅も珍しくない中で、「家で料理をするより外で食べる」ことが、自然な選択として受け入れられてきました。朝食も昼食も、場合によっては夕食も、近所の食堂や茶餐廳で済ませる人が多く、外食は特別な行事ではなく、むしろ日常の延長にあるものでした。
そんな街にあって、かつて「日本発のラーメン」は、外食の選択肢として非常に弱い存在でした。前回触れた通り、“塩辛い”“濃すぎる”という印象が強く、それをあえて食べに行く人は少数派。当時の香港人にとって、外で食べるなら中華、あるいは現地の味つけに慣れた料理が当然だったのです。
一方で、インスタントラーメンの「出前一丁」は早くから香港の家庭に入り込み、日常の中に根を下ろしていました。鍋で3分。味にも慣れていて、なにより「簡単に作れて、片付けも楽」。忙しい朝や、軽く済ませたい夜にはぴったりの存在でした。ブランドとしての認知も高く、「日本のラーメン=出前一丁」のイメージさえあったかもしれません。
つまり、ラーメンという料理自体は知られていたけれど、それを「お店で、わざわざ食べる料理」として捉える文化は、まだ育っていなかったのです。味覚への違和感に加えて、食事スタイルとしての“位置づけ”が見えていなかったことも、日本式ラーメンが広まるまでに時間がかかった理由のひとつでしょう。
ですが、味覚も嗜好も、変わっていきます。食の多様化、旅行経験の蓄積、日本文化への親近感。いくつかの要因が重なり、少しずつ「日本のラーメンを食べに行く」という行動が香港の中に芽生えていくことになります。
その変化の兆しについては、また次回に。
(続)