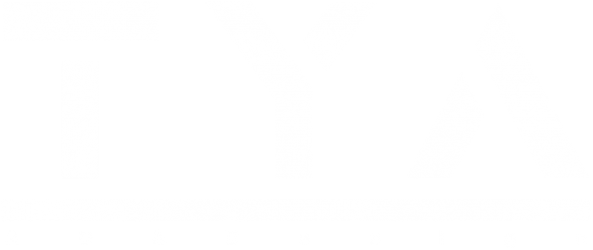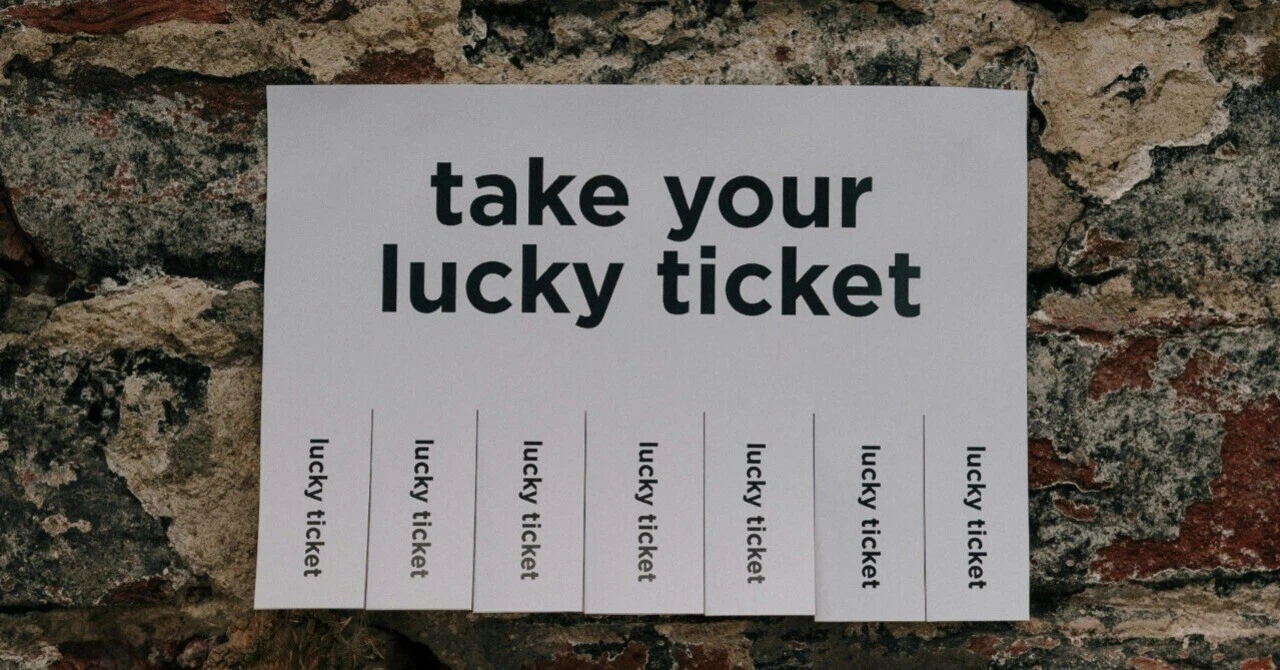
― 継続できなければ、ブランドは育たない
(承前)
前回お伝えした老舗メーカーの事例から見えてきたのは、コンテンツマーケティングの継続性がいかに重要かということでした。 どれほど意欲的にスタートしたプロジェクトでも、チーム内で長期的な視点が共有されていなければ、やがて形骸化してしまう。 そしてその背景には、担当者任せの運営体制と、短期成果への偏重が横たわっています。
🎯 担当者依存のリスク
プロジェクトがうまくいかなくなる要因のひとつに、特定の担当者に依存しすぎる構造があります。特にSNSやコンテンツ関連の施策では、「この人がうまくやってくれているから大丈夫」という空気が生まれやすく、体制の属人化が進みやすい傾向にあります。
しかし、担当者はいつか異動するかもしれませんし、部署ごとの人材の流動性も年々高まっています。その結果、ビジョンの引き継ぎがうまくいかず、プロジェクトが止まってしまう。これは、どの業界でも起こり得る「構造的なリスク」です。
🧩 継続の鍵は“共有”と“仕組み化”
では、そのリスクをどう防ぐか?
答えはシンプルですが、実行には工夫が必要です。プロジェクトの意義やゴールを、チーム全体で共有すること。そしてもうひとつは、スムーズな引き継ぎができる仕組みを日常的に整えておくことです。
たとえば、目的・KPI・コンテンツの方向性・ユーザーとの関係性の変化などを定期的にチーム内で振り返る場を設ける。ドキュメント化やナレッジ共有のツールを活用し、施策の背景や判断の経緯が残るようにしておく。こうした地道な仕組みが、プロジェクトの“温度”を保ち続けるための土台となります。
🧭 短期指標だけで測れない価値がある
もうひとつ大切なのは、すぐに成果が見えないからといって、価値がないと判断しないことです。特にブランド構築やユーザーとの関係性づくりは、“数字”の前に“信頼”を積み上げるフェーズが必要です。
短期のプロモーション施策と並行して、長期的にブランドの世界観や信念を伝える活動を、粘り強く積み上げることが、結果として短期施策の効果も高めることにつながるのです。
🗣 みなさんの現場ではどうしていますか?
属人化、引き継ぎの断絶、短期指標への偏重──こうした課題は、特定の企業だけの問題ではありません。みなさんのチームでは、長期的なプロジェクトをどう継続していますか?チーム内での目的共有、できていますか?
次回は、世代交代に直面した化粧品メーカーの取り組みを事例に、ブランドの“世代を超えた”接続について、さらに掘り下げてみたいと思います。(続)