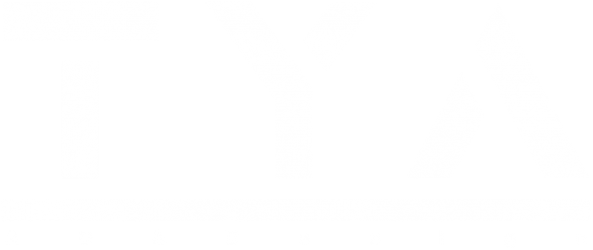― 継続を止めるのは、誰か一人の判断なのか?
(承前)
今回取り上げたいのは、ある老舗メーカーで起きた“ズレ”の例です。業界内での市場シェアは高く、製品力にも定評がある企業でしたが、近年、顧客層の世代交代が進み、これまでのアプローチが徐々に届かなくなっている兆しが見えていました。
そこで私たちは、「ウェルビーイング」と「クオリティオブライフをテーマにしたオンラインコミュニティの立ち上げを提案。ユーザーとブランドが自然につながる場を設けることで、新たな関係性を築くことが狙いでした。
担当者の交代が、すべてを止めた
企画段階では、担当者も非常に意欲的で、**UGC(ユーザー生成コンテンツ)**を活用した投稿企画や、座談会コンテンツなど、ユーザーが自ら語りたくなる仕掛けをいくつも構想しました。ブランドの哲学と生活者の関心が交差する、育てがいのあるプロジェクトだったと思います。
しかし、その担当者が異動となったことで、プロジェクトの意思も一緒に途切れてしまったのです。引き継がれたはずのサイトは、しばらく更新されることなく、やがて完全に放置状態に。せっかく立ち上げた“場”は、静かに役割を終えていきました。
なぜ「継続の仕組み」がなかったのか?
この問題の本質は、「担当者が変わったから止まった」という単純な話ではありません。むしろ、その施策が企業全体としてどう位置づけられていたのか、という点に大きな課題がありました。
つまり、コミュニティサイトが短期的な施策なのか、長期的な戦略資産なのか、その立ち位置が社内で明確に合意されていなかったのです。だからこそ、担当者が変われば優先順位が下がり、誰も責任を持たなくなる。これは一企業だけでなく、多くの組織に共通する構造的な弱点ではないでしょうか。
担当者“頼み”ではなく、組織の意思として続けるには
マーケティング施策の中には、短期で結果が出づらいものもあります。特にコミュニティやUGCのような取り組みは、時間を味方につけて初めて力を発揮する領域です。
だからこそ、最初の段階で「この施策は何を目的とし、どれくらいの時間軸で取り組むものなのか」を、個人ではなく組織として合意しておくことが重要になります。
「担当者が変わっても、なぜこの取り組みが必要なのか」が説明できる状態。それがなければ、どれだけ魅力的なプロジェクトであっても、継続性は脆く危ういものになってしまいます。
継続の鍵は「組織としての視座」
今回のケースから見えてきたのは、マーケティングの継続性が、個人の熱意だけでは成り立たないという現実です。ブランドにとっての“資産”をどう育てていくのか、その視点を持てるかどうかが、企業の未来を左右するのだと思います。
次回は、この事例から得られる教訓と、継続性を保つための仕組みや視点について、さらに具体的に掘り下げてみたいと思います。(続)