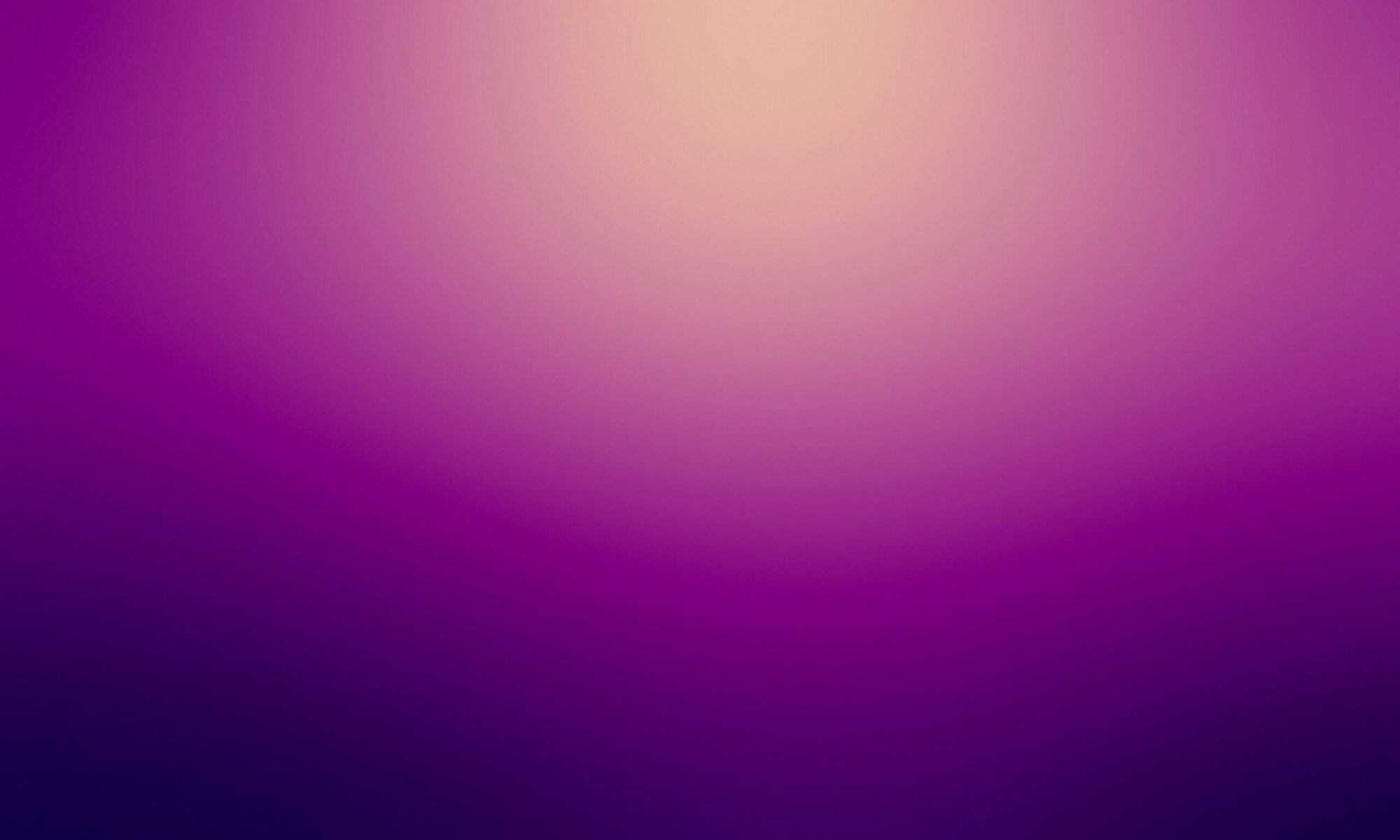企業の中でデザインを内製化する動きは、ここ数年でかなり一般的になってきました。スピード感やコスト面でのメリットを期待して、自社内にデザイナーを抱える体制を整える企業も増えています。その結果、ひとりのデザイナーに多岐にわたる業務を求めるケースも少なくありません。
たしかに、幅広く対応できるオールラウンドなデザイナーは重宝されます。ただし、それが「何でも任せれば大丈夫」という発想になると、話は変わってきます。特に内製チームでは、リソースに限りがあるからこそ、専門性を無視して業務を進めると、結果的にクオリティが下がったり、時間がかかったりと、かえって非効率になることもあります。
さらに注意したいのが、ノン・デザイナーとデザイナーの間に起こりやすい“認識のズレ”です。ノン・デザイナーは、デザインの背景や意図、見た目に現れにくい設計の部分を理解するのが難しく、つい「ちょっと直して」と軽く頼んでしまいがち。一方でデザイナー側も、自分のスキルや思考プロセスを相手に伝える努力を怠ると、すれ違いが生まれてしまいます。
内製チームで良い成果を出すためには、この両者の連携が重要です。お互いの専門性を尊重し、役割分担を丁寧に行いながら、日々のやり取りの中で少しずつ理解を深めていくこと。それが、限られたリソースの中でも質の高いアウトプットにつながっていきます。
次回の最終回では、こうした内製チームやプロジェクトの今後を支える「デザインマネジメントの未来」について考えてみたいと思います。(続)