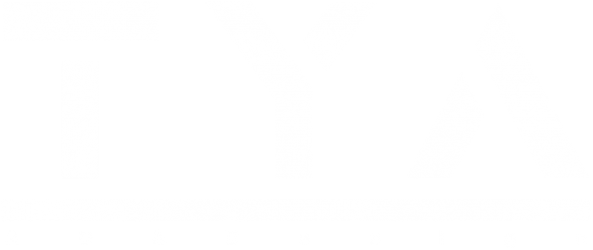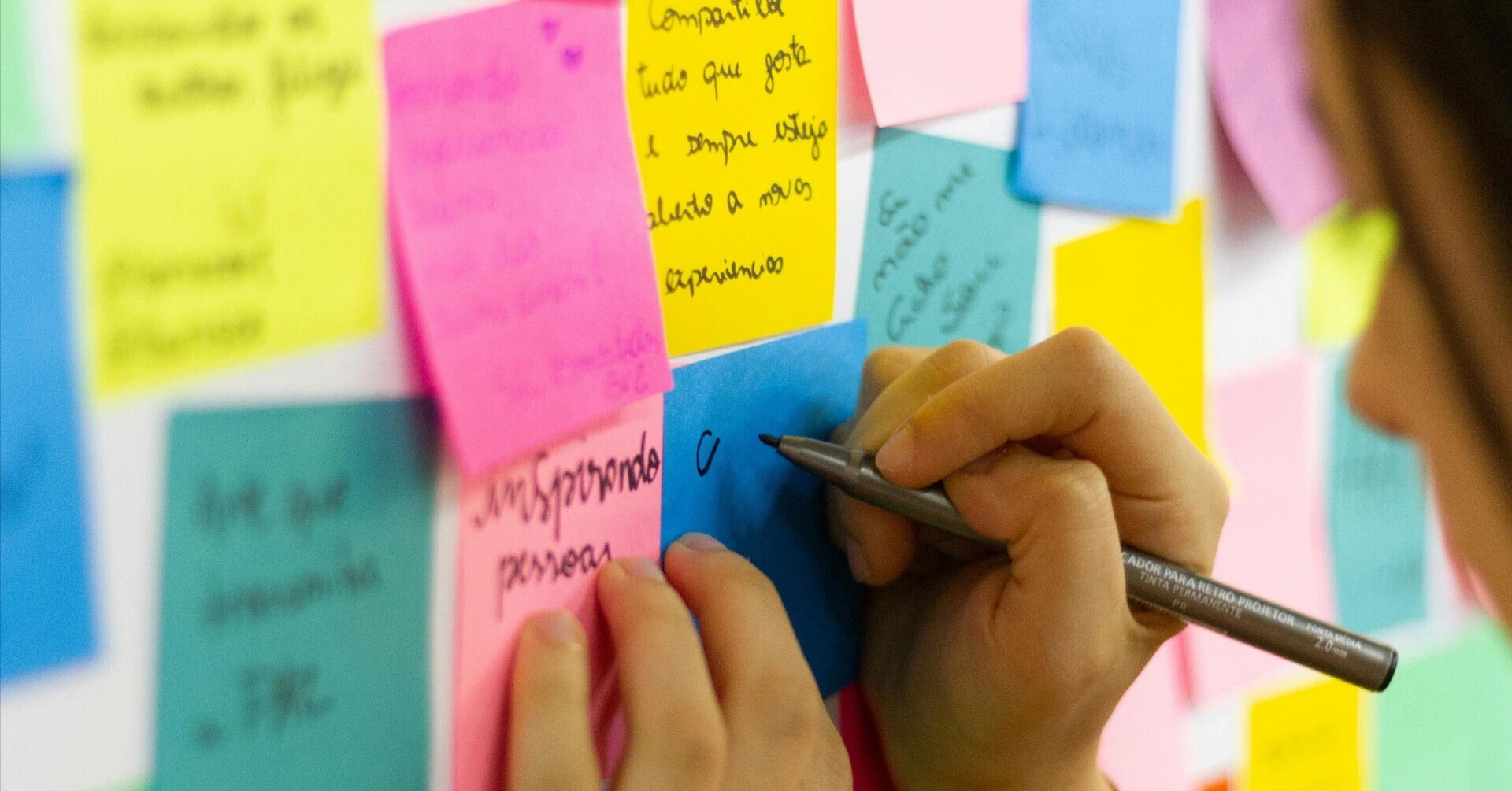日本では訪日外国人向けの販売戦略として定着した「インバウンドマーケティング」。しかし本場アメリカでは、WebやSNS、動画を通じて価値あるコンテンツを提供し、自発的に顧客を引きつけるマーケティング概念を指します。 Continue reading “マーケの種 (17) 「インバウンドマーケティング」”
【香港図鑑17】訊号山訊号塔|尖沙咀の隠れスポット
尖沙咀でふらっと歴史散策:「訊号山花園」
尖沙咀といえば、美しい夜景やショッピングスポットが思い浮かびますが、実はそれだけではありません。喧騒から少し離れた場所に、静かで趣のある散歩スポットが存在します。それが「訊号山花園(シグナルヒルガーデン)」です。尖沙咀の駅から歩いてわずか10分ほどの場所にあるこの公園は、歴史的な建造物と緑豊かな自然が楽しめる穴場スポット。ちょっとした息抜きや散策にぴったりの場所なんです。
Seeds of Marketing (17): “Inbound Marketing”
In Japan, “inbound marketing” has become a well-established sales strategy targeting foreign visitors. However, in its birthplace, the United States, the term refers to a marketing concept that involves attracting customers organically by providing valuable content through websites, social media, and videos. Continue reading “Seeds of Marketing (17): “Inbound Marketing””
マーケの種(16) PDCAだけじゃない?業務改善の手法
【香港図鑑15】 日本製造?
日本薬品の評判と香港市場への挑戦
日本製の薬品はその品質と安全性の高さで、海外市場、特に香港で広く信頼を得ています。香港の薬局やドラッグストアを訪れると、「MADE IN JAPAN」と書かれた製品が棚にずらりと並んでいます。ビタミンサプリ、風邪薬、スキンケア商品など、多様な日本製品が消費者の目を引いている様子は、日本の中小企業が香港市場で一定の評価を得ている証と言えるでしょう。
Seeds of Marketing 16: Is It More Than Just PDCA? Methods for Operational Improvement
マーケの種(15) ブランディングをどうしかしたい!
■「ブランディング!」「ブランディング!」「ブランディング!」
「ブランディングをどうにかしたい」と言う企業は多いですが、その具体的な方向が曖昧なまま進んでいませんか?ブランドの価値をじっくり時間をかけて伝えたいのか、それとも派手な広告で注目を集めたいのか。この2つは全く異なるアプローチです。さらに、どのプラットフォームで展開するかも重要で、これらが社内で共有されていないと、方向性がバラバラになりがちです。 Continue reading “マーケの種(15) ブランディングをどうしかしたい!”
香港図鑑(14)【家政婦の皆さん】
香港を支えるフィリピン出身の家政婦さんたち
約10万人が活躍する大きなコミュニティ
香港には、フィリピン出身の家政婦さんが約10万人も暮らしています。この数字は、香港で暮らす外国人の中で最も多いコミュニティを形成していることを意味します。彼女たちは、共働き世帯や高齢者のケア、さらにはペットのお世話まで幅広い役割を担い、香港の家庭生活に欠かせない存在です。
Seeds of Marketing (15): What Can We Do About Branding?
■ “Branding!” “Branding!” “Branding!”
Many companies say, “We want to do something about our branding,” but aren’t they moving forward without a clear direction? Do you want to take the time to convey the value of your brand slowly and carefully, or do you want to grab attention with flashy advertisements? These are two entirely different approaches. Moreover, deciding which platform to use is crucial, and if these goals are not shared internally, the direction often becomes fragmented. Continue reading “Seeds of Marketing (15): What Can We Do About Branding?”
マーケの種14:「統一したアプローチ」の重要性
SNSマーケティングが普及する中、Instagramはブランドの世界観を伝える重要なプラットフォームです。しかし、その運用方法によっては、かえってブランド価値を損なうこともあります。 Continue reading “マーケの種14:「統一したアプローチ」の重要性”