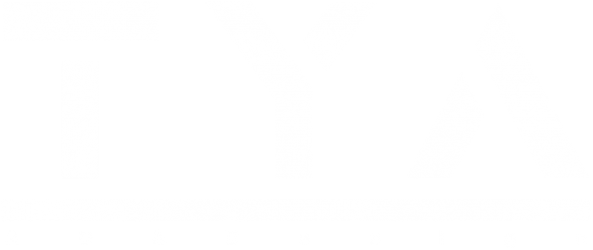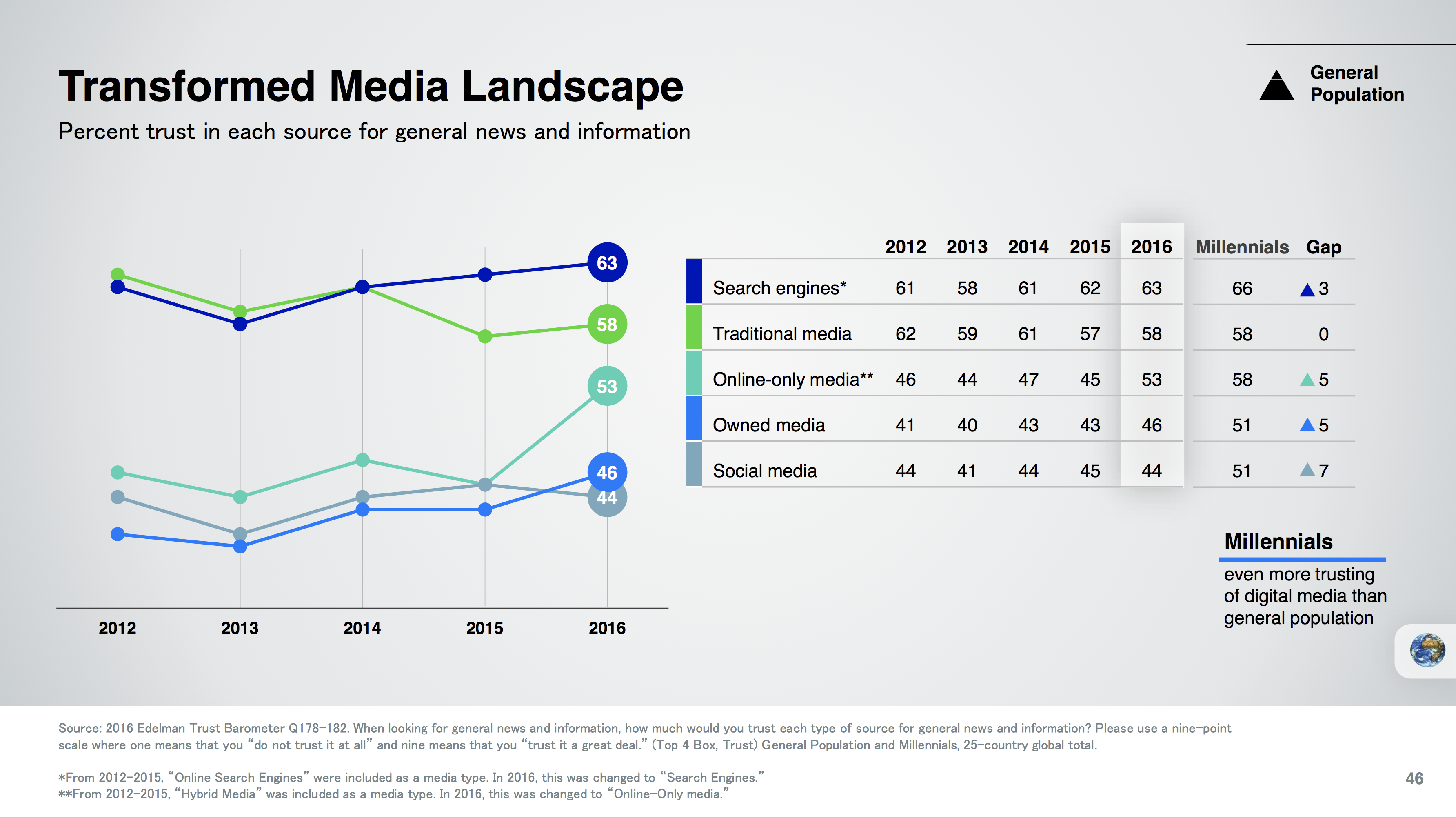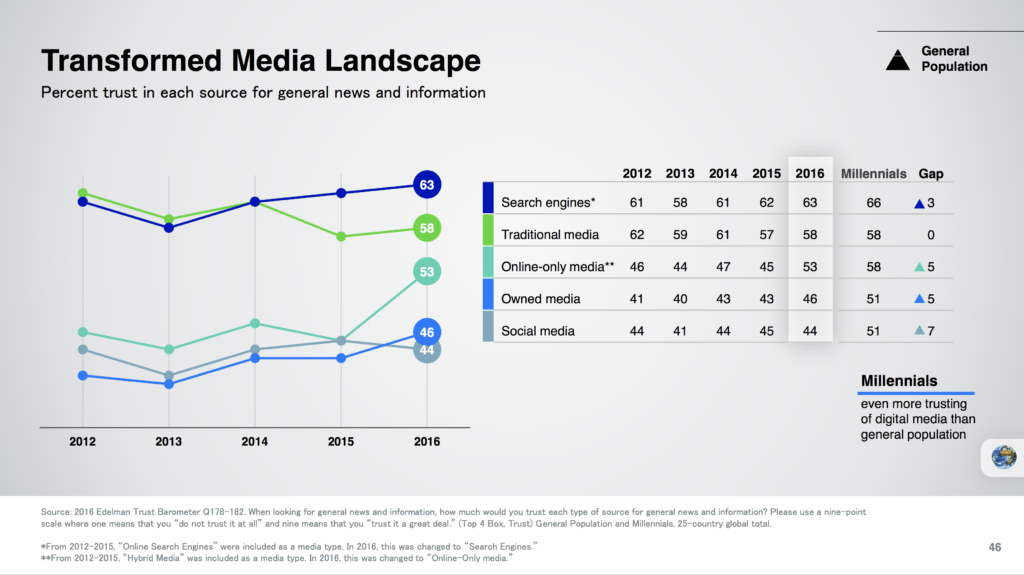司馬遼太郎みたいですね。
真面目な話の中には、息抜きのような回があっても良いかと思います。日本語でブログを書いている以上は、日本の読者の皆様に、香港の魅力を発信していかなければと思うのです。
余談であるが、
本日、オフィスの皆さんに、飲茶に連れて行っていただきました。
香港といえば飲茶、飲茶といえばエビ餃子にシュウマイ……ですが、実はその他にも、美味しい点心はたくさんあります。
実は香港に来るまで、飲茶には興味がなかったのですが、一度行くと虜になってしまいました。日常的に通っているわけではありませんが、少し特別な食事によく使っています。点心の白くてぴちぴちに張りつめたフォルムといい、具は何だろう? というわくわく感といい、とても魅力的ではありませんか?
まずは中華風焼きそば「炒麵」です。イカゲソ入りで、麺が細くパリパリ香ばしくておいしかったです。飲茶屋さんは、点心ばかりではなく、麺やご飯ものも美味しいのです。

これは、「叉燒包」チャーシューまんです。甘辛く煮たチャーシューの細切りが入っています。チャーシューまんは、どのお店でもぱっくり割れた形をしています。どうしてなんでしょう。

「咸水角」ハムソイゴッ、と発音します。甘みのある餅で肉や野菜の餡を包んで揚げたもので、日本語では「もち皮揚げ餃子」と訳されるようですが、個人的には、餃子というより春巻きに近い餡だと思います。昔からある伝統的な点心だそうです。

定番のエビ餃子ももちろん美味しかったですよ! 香港人の友人と飲茶に行くと、よくエビ餃子を勧められます。なぜか、日本人はジャスミン茶とエビ餃子が好き、というイメージがあるそうです。

そして、本日初体験の「蛋散」というデザートを食べました。甘いシロップがかかっていて、サクサクしていて、噛むと一瞬で粉々に崩れます。乾燥させたシュークリームの皮のようなお菓子です。

香港では、飲茶は普段の食事にしては少し高価ですが、日本よりもずっと安く食べられます。有名なチェーン店も美味しいのですが、個人的には郊外にあるような老舗が、素朴で親しみやすい味がして好みです。しかしどのお店も点心やお茶に豊富な種類があり、どれも美味しくて、やはり食文化は本場が最も豊かだと感じさせられます。