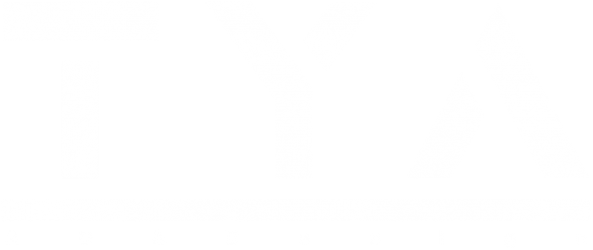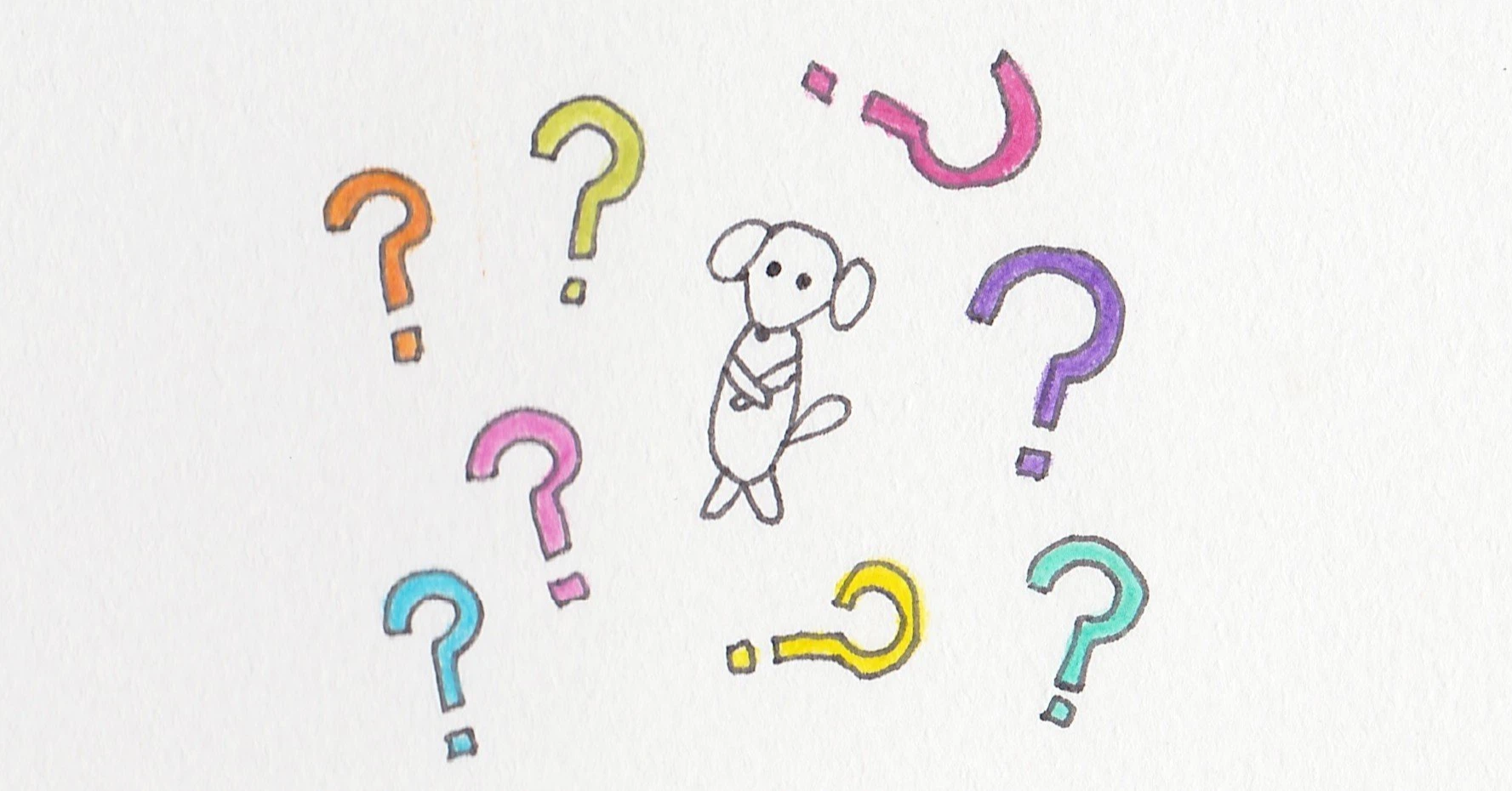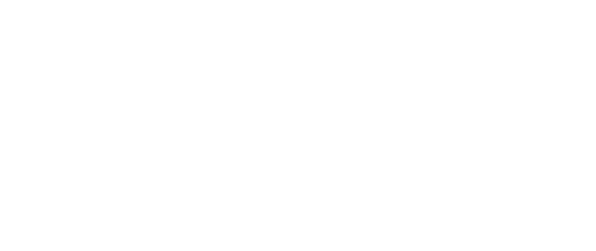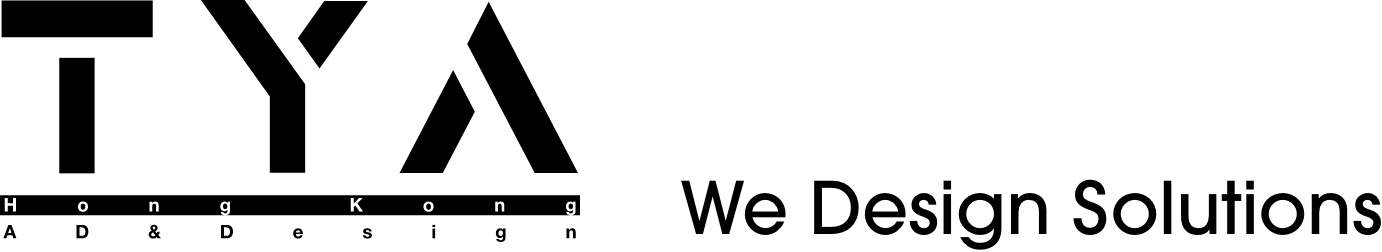広告を出す際には、「この広告で何を達成したいのか」という目的を明確にすることが重要です。「認知拡大」「購入促進」「好感度向上」など、目的によって広告の内容や配信方法、ターゲット設定が大きく変わります。
香港図鑑3:強襲揚陸船・海南
香港島の西に位置するこの埠頭。かつては外国の軍用船が頻繁に停泊し、歴史の中で幾度となく国際的な動きの舞台となった場所です。そのような歴史ある埠頭に、先週久しぶりに停泊したのは、中国海軍の現代的な大型軍艦「海南」でした。 Continue reading “香港図鑑3:強襲揚陸船・海南”
Seeds of Marketing 4: Clarifying Advertising Objectives
When running an advertisement, it is crucial to define what you aim to achieve. Objectives such as brand awareness, purchase promotion, and favorability improvement significantly influence the ad’s content, distribution method, and target audience. However, many marketers express a desire to achieve all objectives simultaneously—expanding awareness, driving purchases, enhancing brand perception, and deepening customer understanding all at once. Continue reading “Seeds of Marketing 4: Clarifying Advertising Objectives”
香港図鑑(2)クロスハーバートンネル
香港海底隧道。香港島と九龍半島を結ぶトンネル、つまりビクトリアハーバーを横断する海底トンネルをご存じですよね。たった数分でこちらからあちらに移動できる便利なルートですが、なぜか心理的なバリアがあって、移動が億劫に感じることがよくあります。 Continue reading “香港図鑑(2)クロスハーバートンネル”
マーケの種 3:チーム内の目標を一致させよう
「ブランディング強化」という共通の課題に取り組む際、メンバーそれぞれが異なる目標を掲げてしまうことはよくあります。例えば、ある人は「バズるコンテンツ」を作ることが重要だと考え、別の人は「長期的な発信」を重視し、さらに他の人は「ロゴやデザイン」などの意匠に目を向けます。それぞれの基点が異なるため、目指すゴールやアプローチがばらばらになってしまうのです。 Continue reading “マーケの種 3:チーム内の目標を一致させよう”
Seeds of Marketing 3 : Aligning Team Goals
When working on a shared challenge like strengthening branding, it is common for team members to set different objectives. For example, one person may prioritize creating viral content, another may focus on long-term messaging, while someone else may emphasize logos and design elements. Continue reading “Seeds of Marketing 3 : Aligning Team Goals”
香港図鑑1:燒臘
豚さん、鴨さん、イカさん。香ばしい香りをまとった彼らが、丸焼きだったり半身だったりと、透明なガラスケースの向こうにぶら下がっています。黄金色に輝く皮はパリッと、身はジューシーで、見るだけで食欲をそそる美味ローストたち。この光景は、香港の街角でよく目にする、食文化の象徴とも言える風景です。 Continue reading “香港図鑑1:燒臘”
マーケの種 1:顧客理解が最重要
顧客を深く理解するためには、表面的なデータや一時的なトレンドに頼るのではなく、あらゆる角度から顧客の行動や思考を捉える努力を惜しまないことが重要です。顧客がどのような背景で商品やサービスを選び、利用しているのか、そしてどのような課題や期待を抱えているのかを知るためには、多様なアプローチを組み合わせる必要があります。 Continue reading “マーケの種 1:顧客理解が最重要”
Seeds of Marketing 1: Understanding Customers is the Top Priority
To deeply understand customers, it is crucial not to rely merely on surface-level data or fleeting trends. Instead, one must make a continuous effort to grasp customer behavior and thought processes from multiple perspectives. Understanding why customers choose and use a product or service, as well as identifying their challenges and expectations, requires a combination of diverse approaches. Continue reading “Seeds of Marketing 1: Understanding Customers is the Top Priority”